実施例の後出しが認められた判決(日焼け止め剤組成物事件)のような驚きの判決が、その後の実務に与える影響について日本とアメリカを比較します。
特許訴訟は、日本では知財高裁が、米国ではCAFCが専属管轄であり、どちらも原則は三人で審理するところも同じです。また、全員で審理を行う大合議制度、en banc制度があるところも同じです。
以下、異なる点を説明します。
1.日本
日本では、通常の知財高裁判決には先例としての価値はほとんど全くないと言えると思います。その意味では上記の日焼け止め剤組成物事件もただの一判決であり、今後の実務には影響しないだろうと考えて無視することもできるかも知れません。但し、例外がいくつかあります。
(1)最高裁判決が出された場合
上告されて最高裁判決が出された場合は、拘束力のある判例となり、今後は最高裁自身が判例変更するまでは誰も逆らうことができません。
(2)知財高裁の大合議判決が出された場合
知財高裁の大合議は、知財高裁の全ての部の部長が集まって知財高裁としての統一的見解を出すための制度ですので、大合議判決はが出された後は、実質的に、その後の各部の判決の内容を拘束すると思われます。
(3)判決の内容が審査基準に取り込まれた場合
裁判例が審査基準に取り込まれるかどうかが実務に与える影響は極めて大きいです。審査官は、審査基準に従うことが推奨されていて、個々の知財高裁判決に従うことが推奨されている訳ではないので、判決の内容が審査基準に盛り込まれているかどうかは審査官の心証に与える影響は極めて大きいと思われます。上記の日焼け止め事件の判決内容が仮に審査基準に盛り込まれれば、今後の実務に与える影響は絶大ですが、盛り込まれなければそのうち忘れ去られていくと思います。
別の機会に詳しく書きますが、優先権主張に関して、人工乳首事件という極めて重要な事件があります。一言でいうと、国内優先権主張をして実施形態を追加すると、先の出願と後の出願の間の引例によって先の出願が拒絶されるという衝撃的なものです。その論旨も難解で結論も非常に難解なものですが、審査基準に盛り込まれてしまったので、特許庁の公式見解のようになってしまいました。しかも、国内優先権に関する判決なのに、パリ優先にまで拡張されてしまいました。パリ条約との関係も少し心配になる判示内容です。
日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合(日本出願に発明の実施の形態が追加される場合等)
第一国出願の出願書類の全体には記載されていなかった事項(新たな実施の形態等)を日本出願の出願書類の全体に記載したり、記載されていた事項を削除(発明特定事項の一部の削除等)する等の結果、日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合は、その部分については、優先権の主張の効果は認められない。
(参考:東京高判平15.10.8、平成14年(行ケ)539号審決取消請求事件「人工乳首」)
2.米国
米国のCAFCには裁判官が15人いて、各事件は、三人で担当しますが、各事件での判決は、その後のCAFCの裁判官を拘束します。同じ論点に遭遇した裁判官は、自分の考えがどうであれ、過去のCAFC判例に拘束されます。事件名は忘れてしまいましたが、3人中ともが自分の書いた判決に反対意見を書いたという判決もあります(事件名が分かる方がいたら教えて下さい。)従って、米国の判例法がどのように形成されていくかは、重要事件の担当が誰になったかによって影響を受けるので、ある意味では偶然に左右される要素があります。
一旦形成されたCAFC判例を変えるには、en bancによる手続きを経る必要があります。en banc審理は、CAFCのメンバーの過半数がen banc審理を行うことに賛成したときに開始されます。従って、現行の判例を変更したい判事は仲間を集めて、en banc審理を開始することを試みます。有名なケースでは、1997年のLilly事件において、Lourie判事が補正や優先権が関与しない事案について初めて記述要件(written description requirement)を適用したところ、Rader判事は、この考えに一貫して反対して判例変更を行うために、en banc審理を何度も請求しましたが、その希望はかないませんでした。つい最近のAriad判決では、en banc審理で記述要件が特許要件に含まれることが確認されてしまいました。
このように米国では、各判決は非常に強い先例価値を有しています。
3.まとめ
以上のように、日本の法制度では、例外的な場合を除いて、各判決の先例性は高くないと思われますので、日焼け止め事件の位置付けも今後の成り行きを見守る必要があると思います。
知財高裁の判事間で法律の解釈が分かれた有名な例は、訂正請求があった場合の特許性判断が請求項毎に行われるべきかどうかについてです。訂正請求は、無効審判中の一手続きですが、訂正審判によく似ています。無効審判では、特許性判断は請求項毎に行われ、訂正審判では、全請求項一括で行われるので、訂正請求の場合にどうなるのかが知財高裁の判事の間で分かれました。この問題は、最高裁が、請求項毎に判断すべきと判示したことで決着しました。日焼け止め事件での実験成績証明書の取り扱いについても同様に最高裁で決着がつけられるかも知れません。
ブログ

人気記事
-

自己指定のススメ
2010.07.12
-
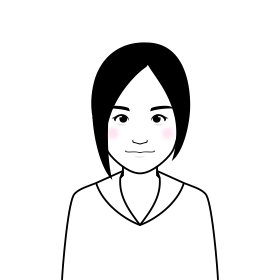
アメリカ 3つの継続性出願の違い(分割/継続/一部継続)
2016.08.15
-

毎日業務改善(サンダーバードで開封確認を要求する設定を簡単に行う)
2013.12.16
-

欧州特許(EPO)維持年金 期限
2012.02.23
-
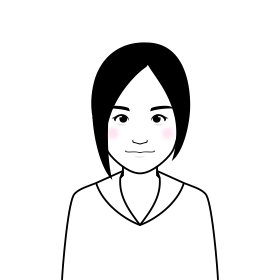
アメリカ年金期限が『3.5年』と半端である件
2018.04.19
