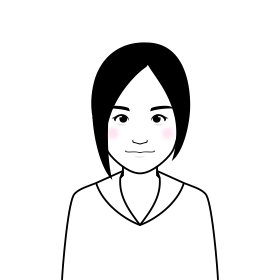外国出願する際のクレームの書き方は、大きく分けて1パート形式と2パート形式に分けられます(2パート形式は、ジェプソンクレームとも呼ばれます)。この記事では、それぞれの形式の特徴と、外国出願の際にどちらの形式でクレームを記載すべきかについて書いています。
1パート形式と2パート形式について説明するために、まず、英語で書かれたクレームの一般的な構成について説明します。クレームは、前提部(preamble)、移行部(transitional phrase)、本体部(body)の3つから構成されています。例えば、
A plastic package comprising:
front film; and
back film,
wherein the front film and the back film are sealed together at a bottom sealing portion and a pair of side sealing portions.
というクレームがあったとすると、前提部は“A package package”、移行部は“comprising”、本体部は“front film”及び“back film”並びに“wherein”以降の(“front film”及び“back film”を詳しく説明している)部分に相当します。
1パート形式は、前提部と本体部において、発明の公知の内容と新しい内容(特許性のある内容、例えば、発明の「特別な技術的特徴」)を書き分けずに、自由に混ぜて記述する形式です。一方で、2パート形式は、公知の内容を前提部に、新しい内容を本体部に、分けて記述する形式です。また、2パート形式では、公知の内容と新しい内容をつなぐ部分に、以下のような特徴的な表現が使われます。
“characterized by”
“characterized in that”
“the improvement comprising”
“wherein the improvement comprises”
上で例示したクレームを2パート形式で書くと、例えば、以下のようになります。
A package package, comprising:
front film; and
back film,
characterized in that, the front film and the back film are sealed together at a bottom sealing portion and a pair of side sealing portions.
このように書くことで、“front film”と“back film”を含む“plastic package”は公知の内容だけど、それらがどのようにシールされているがこの発明独自の新しい内容であると主張していることになります。
ここまで、1パート形式と2パート形式のクレームについて簡単に説明しました。以上からお分かりのように、2パート形式では、公知の内容(上の例では“characterized in that”より前に記載の内容)には特許性がありませんと自白したと判断されるため、Office Actionにおいて発明者にとって不利な認定を受ける可能性があります。欧州出願では、2パート形式が推奨されていますが、それに従う義務はないため、欧州を含む外国出願では、通常の1パート形式で書いて出願したほうが、発明者の利益となる可能性が高いです。
ここで、2パート形式特有の表現である“characterized by”と全く同じに訳されてしまう日本語表現として「~を特徴とした」があります。例えば、「○○を有することを特徴とした」は“characterized by comprising ○○”などと訳されることが多いようです。“characterized by”を使ったからといって、ただちに2パート形式だと誤解される可能性は低いと思いますが、次の二つの理由から、“characterized by”は使わないほうが良いと思います。1つ目は、念のため安全側で使わないという理由です。2つ目は、「~を特徴とした」という日本語表現自体があまり意味を有さないという理由です。つまり、「~を有することを特徴とした」という表現は、単に「~を有する」に省略してしまっても、何も意味を失わないということです。よって、「~を有することを特徴とした」の訳としては、“characterized by”を使わずに、単に“comprising”で良いことになります。
以上、1パート形式と2パート形式のクレームについて簡単にまとめました。外国出願では、基本的に1パート形式でクレームを記述したほうが良いと思います。
参考文献:倉増一、特許翻訳の基礎と応用―高品質の英文明細書にするために―、講談社、2006年